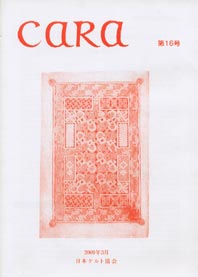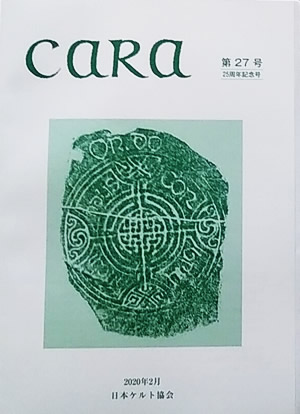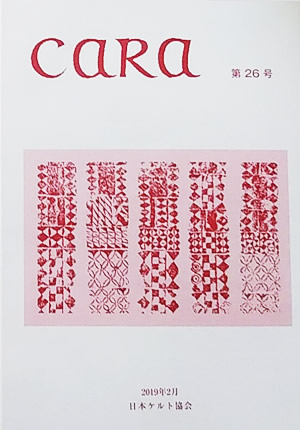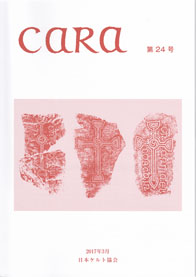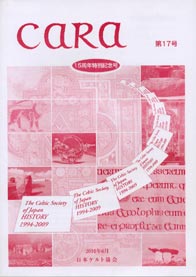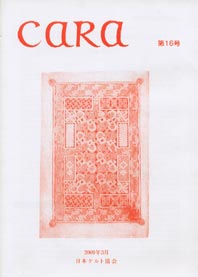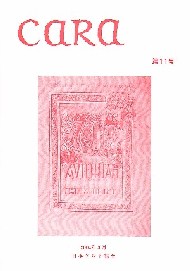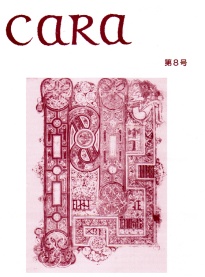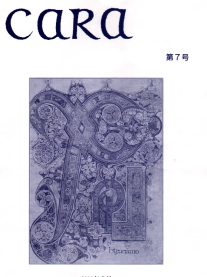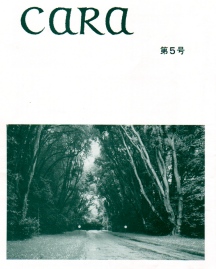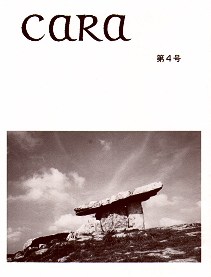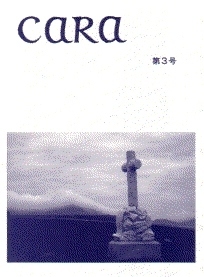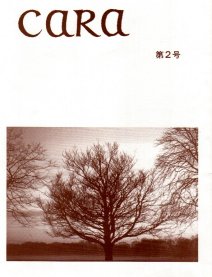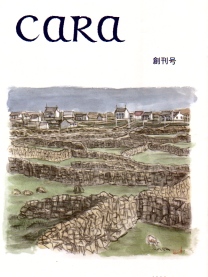「ケルトの笛の世界」コンサート
アイリッシュ・フルート、ティン・ホイッスルなどを駆使し、時代と地域を越えてケルトの音楽をスケッチするケルトの笛演奏家、hatao(畑山智明)さんの福岡では初めての本格的なコンサート。10年前に映画「タイタニック」を見て以来、ケルトの笛のとりこになり、アイルランド、スコットランド、ウェールズ、イングランド、フランスのブルーターニュなど・・・旅して学んだ旋律の数々をnami(上原奈未)さんのピアノアンサンブルとともにお楽しみください。
翌5月23日にはアイルランドのたて笛「ティン・ホイッスル」入門公開講座を予定しています。どうぞ奮ってご参加ください。
| 演 奏 | 笛・畑山智明氏 ピアノ・上原奈美 氏 |
| 場 所 | 九州キリスト教会館 ホール(4F) 福岡市中央区舞鶴2-7-7 ℡092-712-6808 |
| 日 時 | 5月22日(土)18:30~20:30 開場18:00 |
| チケット | 前売り 2500円 (学生前売り 1500円) 当日券 3000円 (学生当日 2000円) |
| 主 催 | 日本ケルト協会 |
| 後 援 | 福岡市、福岡教育委員会 (財)福岡市文化芸術振興財団 (財)福岡県国際交流センター 福岡EU協会 朝日新聞社 読売新聞西部本社 FM福岡 LOVEFM 天神FM クロスエフエム |