
■アイルランドみやげ話
-2009-2010~モノたちが語るダブリン
栩木伸明
■ブリテン島
-新石器時代・青銅器時代の埋葬と社会
溝口孝司
■アイリッシュダンスの歴史的変遷
山下理恵子
■スコットランドのバグパイプと
ケルト文化における位置づけ
山根 篤
■会員投稿
ハーン来日120年後の松江を訪ねて
筒井正二郎
■アイルランド通信
「アイルランド語学習事情・イン・デリー」
大倉純子
会報誌CARAバックナンバーご紹介
※購入をご希望の方は事務局にお問合せ下さい。

■アイルランドみやげ話
-2009-2010~モノたちが語るダブリン
栩木伸明
■ブリテン島
-新石器時代・青銅器時代の埋葬と社会
溝口孝司
■アイリッシュダンスの歴史的変遷
山下理恵子
■スコットランドのバグパイプと
ケルト文化における位置づけ
山根 篤
■会員投稿
ハーン来日120年後の松江を訪ねて
筒井正二郎
■アイルランド通信
「アイルランド語学習事情・イン・デリー」
大倉純子
会報誌CARAバックナンバーご紹介
※購入をご希望の方は事務局にお問合せ下さい。
アイルランド文学ジェームズ・ジョイスの有名な作品「ダブリン市民」を原書で読んでいきます。
この輪読会では『ダブリン市民』のなかでも比較的読みやすい作品をいくつか取り上げ、原文で精読していきます。 ジョイスに興味があり、その文学世界を知りたいと望んでいらっしゃるかたはこの機会をぜひお見逃しなく!
| 講 師 | 帝京大学教授 日本ケルト協会会員 木村俊幸氏 |
| 日 時 | 毎月第1金曜日 18:00~19:30 |
| 場 所 | The Celts(ザケルツ) 福岡市中央区警固1-1-23 KIKUEビル1F ℡092-714-0112 |
| 参加費 | 各回1000円 |
| 定 員 | 10名 会員を対象とした少人数の学びの会です。 途中からの参加も可能です。 なるべく早くお申し込みください。 担当:稲永℡ 092-812-0939 |
John John Festival & baobab aruk band
ケルト・アイリッシュ音楽シーンで
いま、ノリノリの”John JohnFestival”と聴かせる”baobab aruk band”の2つのグループを迎えてのケルト・アイリッシュ音楽祭。優しい旋律が、軽快なリズムが、時には哀しみに満ちて・・・。
深い森の中で奏でるケルト・アイリッシュの音色。その魅力と醍醐味を住吉神社能楽殿で、たっぷりとご堪能下さい。
John John Festival
こよなくアイルランド音楽を愛する3人組。
フィドル、ギター、うた、それにプラスしてアイルランドの太鼓バウロンで奏でる音楽は圧巻、聴きごたええ十分です。
今回はCD発売記念ツアーとして、参加サポートミュージシャン2名を加えた、初のフルバンド編成で楽しさ満載です。
また、映画「ハナミズキ」にもグループの中の2名が楽隊で参加しています。
baobab aruk band
ケルトミュージックを中心に、古楽器から現代楽器、トラディショナルからポップスまで自由に伸びやかに演奏します。自然の中で見た景色や感覚を音にかえる、まるでマジシャンのようです。
その音色はあくまでも魅力的。2005年には「愛・地球博」出演。2007年ニュージーランド20公演の海外ツアー。九州の地で生まれたサウンドを存分にお楽しみ下さい。
| 場 所 | 住吉神社 能楽堂 福岡市博多区住吉3-1-51 ℡092-291-2670 |
| 日 時 | 12月19日(日)14:00~16:00 開場13:30 |
| チケット | 前売り 3500円 当日券 4000円 全自由席 |
| 主 催 | 日本ケルト協会 |
| チケット | 取り扱い チケットぴあ ローソンチケット The Celts 他 |
| 後 援 (予定) |
福岡市、福岡教育委員会、(財)福岡市文化芸術振興財団、 ((財)福岡国際交流協会、朝日新聞社、毎日新聞、読売新聞西部本社 福岡文化連盟、RKB毎日放送、KBC九州朝日放送 Love FM、FM福岡、天神FM、クロスFM 他 |
| 東京パイプバンド代表 Pipe Magor | 山根 篤氏 |
| 日本スコットランド協会理事 |
スコットランドのハイランド地方を旅すると、広大な丘、ヒースの草原、羊たち、そして運河や湖、城(廃墟となってしまったものも含め)に出会うことができる。
各種族によって統治されていた土地には、その種族の長であったクラン(家系)があり独自のタータンが存在し、異までもなお大切に守られ、勇猛果敢なスコットランド人であることへの誇りとして子孫たちへと受け継がれている。
1974年女王陛下来日を機に設立された東京パイプバンドの代表として30年以上国内外でハイランドバグパイプの演奏活動を続けているが、演奏曲目の中には現代的な軍隊の行進曲だけではなく、ダンス曲・古典曲・歌唱曲・生活の場面に根付いた曲も多い。スコットランドにおいて英国軍となる以前はスコットランド内の各クラン(種族)の城主に帰属していたバグパイパーたちが、生活に根付いた各場面で演奏をしていた。これは、唯一英国より独自の軍隊(私有軍)を持つことを許されAtholl侯爵とAtholl Highlandersの存在からも当時の様子を目の当たりにすることができる。今回の講座では楽曲の違い・様々な経験や楽器の近年の変化を、実際の楽器を使って実際に鑑賞していただく。
また、ハイランドバグパイプ発祥の地とされるスカイ島、ここにあったバグパイプ学校とマクリモン家・国民詩人として有名なロバート・バーンズにも触れながら、バグパイプという楽器の生い立ちと、現在スコットランドだけでなく世界中で演奏されたいるその姿を様々な角度からご紹介したい。
| 日 時 | 2010年11月28日(日) 13:30~16:30 (展示のみ12:00~) |
| 内 容 | 13:30~14:00 ケルト文化とアイルランド~映画『地球交響曲第一番』に観る 日本ケルト協会 山本啓湖 14:00~15:30 「スコットランドのバグパイプとケルト文化における位置づけ」 東京パイプバンド代表 山根篤 15:30~15:45 スコティッシュダンス 原田秀子ほか 15:45~16:30 アイリッシュダンスト音楽 ザ ケルツ セッションバンド/プラブサノール アイリッシュダンスクラス有志 アイルランド紅茶試飲 |
| 場 所 | (財)福岡県国際交流センター こくさいひろば <アクロス3F> 福岡市中央区天神1-1-1 TEL092-725-9200 |
| 参加料 | 一般・会員共 無料 |
| 主 催 | 日本ケルト協会 |
当会では1996年から折りに触れてアイリッシュダンスの講座を開いてきました。
昨年に引き続いて元Riverdanceダンサー 林孝之さんの公開講座を行います。
林さんはリーバーダンスに感銘を受け、2001年に単身アイルランドに渡り、ダンススクールに通い、世界選手権などに出場。リムリック大学で本格的に伝統舞踏コースを修了し、リバーダンスのメンバーとして世界ツアーに参加されています。
昨年はミュージカル「パイレーツクィーン」にも出演されました。
特にこの講座のために2010年11月~2011年4月にかけて来福をお願い致しました。
初心者クラスは全く経験がない方でもわかりやすく基礎から指導して頂きます。年齢制限もありません。
この機会にアイリッシュダンスを始めてみませんか!経験者クラスは今までの当会のダンス講座が受けられた方やダンスの経験のある方が対象です。
ぜひこの機会をお見逃しなく!
| 講 師 | 元Riverdanceダンサー・振付師 林 孝之氏 |
| 日 時 | 11月14日(日) |
| 場 所 | 福岡市内の体育館、アクロス福岡練習室などを予定。 2回目の日時については随時お知らせいたします。 |
| 参加費 | 初心者クラス 一般8,000円 〈会員6500円〉 経験者クラス 一般9,000円 (会員7500円) 〈服 装〉動きやすいもの |
| 主催 | 日本ケルト協会 |
| 自主練習 | |
| 場 所 | 中央体育館など (健康体力相談室) 福岡市中央区赤坂2-5-8 ℡092-741-0301 |
| 開催は | 会場の都合により変更になる場合もあります。 その場合は早めにお知らせいたします。 |
| 初心者クラスは | 全く初めての経験がない方でも判りやすく基礎から指導していきます。 |
| 経験者クラスは | 今まで当会のダンス講座を受けられた方やダンスの経験がある方が対象です。 |
| 詳細は | 直接担当者へ 森下:harry_morishita@live.jp |
今から1万2千~2万3千年前にかけて、日本列島に縄文文化が花開きました。およそ1万年に及ぶ縄文時代は、金属を持たない森の文化でした。生命を敬い、自然の営みと共に歩んだその長い歴史は、豊かな列島文化の特色でもあり、また現代注目されているエコロジー社会のまさに先駆けだったといえます。
雄大な森林地帯を背景として熟成された信州の縄文文化は、地域ごとに多様性をもつ列島の縄文文化の中でも、象徴的な存在として異彩を放っていました。数多くの遺跡に残された芸術作品ともいえる遺物からは、独創的で重厚な美しさの中にも、けして閉鎖的だはないおおらかな命のうねりを感じることでしょう。
この旅では、著名な博物館での資料見学だけではなく、史跡公園となっている縄文時代の黒耀石鉱山の散策や、縄文人たちの技にチャレンジする体験コースも計画しております。大自然の中、悠久の時を越え、その知恵と心に触れてみましょう。
| 10月1日(金) | 福岡空港8:30発 ー 名古屋11:51着 ー 塩尻駅着13:52 ー諏訪市博物館 ー 富士見町井戸尻考古館 ー 諏訪市諏訪大社
ペンション「おはようパウロ」泊 |
| 10月2日(土) | 宿舎9:00発 - 茅野市尖石縄文博物館 - 黒耀石体験 ミュージアム&史跡公園 -(昼食) -星糞峠の黒耀石鉱山発掘現場 ペンション「おはようパウロ」泊 |
| 10月3日(日) | 宿舎8:00発 -9:30御代田町浅間縄文ミュージアム - 11:30千曲市森将軍塚古墳館 - (昼食) - 長野県立歴史館 -篠ノ井駅発15:09 -名古屋駅18:01 - 名古屋駅18:15 - 博多駅21:44着 |
| 集合場所 | JR博多駅 中央改札口 AM8:00 |
| 現地講師 | 黒耀石体験ミュージアム学芸員 大竹幸恵氏ほか |
| 定 員 | 15名(最低催行人数5名) |
| 参加費 | 一般70.000円 会員68,000円(福岡発着) 一般28.300円 会員26.300円(現地集合) |
| 企 画 | 日本ケルト協会 |
| 旅行取り扱い | (株)JTBトラベル九州 福岡営業所 (福岡県知事登録旅行業代理業31号) |
| 予約お押し込み | 氏名、住所、連絡先、メールアドレスなどをご明記の上 FAX又はメールで9/10迄に事務局へ。 参加料は出発日の2週間前までにお支払いください。 郵便振込み口座01780-19650 |
| 事務局 | 〒816-0882 福岡市博多区麦野1-28-44 ℡ FAX 092-574-0331 http://www.celtic.or.jp keiko-y@celtic.or.jp |
関西外国語大学、立命館大学非常勤講師 翻訳家 山下理恵子氏
Round the house and mind dresser
私自身がアイルランドで体験したダンスは、華やかなスポットライトを浴びたダンスショーでも、少女たちが順位を競い合うステップ・ダンスでもありませんでした。真冬の暗い空の下、パチパチと音を立てる暖炉の近くで奏でられる音楽、そしてダンス。仕事帰りにダブリンから車を走らせて、週末に参加した田舎での熱気あふれるケイリーやセッション。「食器戸棚にぶつからないように気をつけな!(mind the dresser)」という踊るときの決まり文句の通りの、昔ながらの光景。現在では大きなステージやパブの出し物として人気の高いアイリッシュ・ダンス。でもダンスが人々の目に触れられるようになったのはつい最近のことです。「アイリッシュ・ダンス」という名称で呼ばれるようになったのも100年ほど前から。それまでは市井の人たちの、生活の中で根付いた文化でした。ちょうど私がアイルランドで体験したような・・・。これらのダンスから、テレビや舞台で多くの人が目にするアイリッシュ・ダンスが生まれたのです。そしてこれらのダンス、例えば通常4組で踊るセット・ダンスやコネマラ地方のシャン・ノースなどはいつまでもアイルランドで踊り継がれています。どのような種類のアイリッシュ・ダンスを踊る上でも、知っておくべき伝統だといっても過言ではありません。
今回の講演では、アイリッシュ・ダンスの歴史をその時代の社会情勢を絡めながら説明していきます。また、私自身のアイルランドでのダンスに関わる楽しく、時には悲しい経験談もお話ししたいと思います。アイリッシュ・ダンスを踊る人には、政治に翻弄されたダンスの社会的背景をぜひ知ってほしい。踊ったことのない人は、ダンスの幅の広さ、生活の中での役割、そして楽しさを聞いて、実際に踊ってみてください。
| 日 時 | 2010年9月12日(日) 第1部14:00~15:30講演(13:30開場) 第2部16:00~18:00アイリッシュ・ダンスワークショップ |
| 場 所 | 婦人会館 大研修室<あいれふ9F> 福岡市中央区舞鶴2-5-1 |
| 参加料 | 一般 1,500円 会員 無料 *当日 会場で直接受付けます。 |
| 主 催 | 日本ケルト協会 |
| 後 援 | 福岡市 福岡市教育委員会 |
九州大学准教授 溝口孝司氏
現在のイギリス(連合王国)の主要部を占めるブリテン島、なかでもウイルトシャー・ドーセットの二州を中心とする南部イングランドの地で、新石器時代から青銅器時代の前半にかけて(今から約6000~3500年前)、特異な葬送文化が発達した。最近の調査では、有名なストーンヘンジも、死者の葬送の場として機能していたことが確かめられている。
最新の考古学の成果は、当時の人々が、さまざまな儀式を通じて、死者や祖霊と親しく交流することによって、文化や社会の仕組みを維持し、生活していたことを明らかにしている。
本日は、当時の埋葬の場やストーンヘンジの発掘調査の成果をもとに、ケルト以前のブリテン島の文化や社会について考えてみたい。
| 日 時 | 2010年7月11日(日)14:00~16:00(13:30開場) |
| 場 所 | あいれふ講堂<10F> 福岡市中央区舞鶴2-5-1 |
| 参加料 | 一般 1,500円 会員 無料 *当日 会場で直接受付けます。 |
| 主 催 | 日本ケルト協会 |
| 後 援 | 福岡市 福岡市教育委員会 |
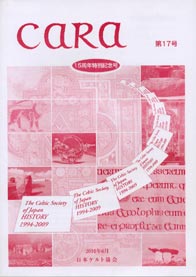
■水上往還
-アイルランドにおける航海譚と異界の風景
松村健一
■ケルトの水脈
-ブルターニュ(ブレイス)が
ケルトを意識するとき
原 聖
■漢とローマ-倭とケルト
西谷 正
■15周年記念行事
「ケルト・アイリッシュ音楽とダンスのつどい」
「ケルト・アイルランド文化の交流展」
「ブレンダン・スキャネル
駐日アイルランド大使歓迎会」
■会員投稿
「ダブリン市民」のように博多を歩いてみる
山本啓湖
■アイルランド通信
「アイルランドイースター事情」
織田村恭子
会報誌CARAバックナンバーご紹介
※購入をご希望の方は事務局にお問合せ下さい。
アイルランドで演奏されているたて笛ティン・ホイッスルは、誰でもすぐに音を出すことができ、指遣いも簡単です。
ケルトの美しい曲や楽しいダンス曲を、基礎から丁寧に手ほどきします。
楽器は1500円程度で手に入りますので、音楽が未経験の方もお気軽にご参加ください。
貸し出し楽器もあります。グループレッスンで90分を予定しています。
| 講 師 | ケルト笛演奏家・畑山智明 氏 |
| 場 所 | The Celts(ザケルツ) 福岡市中央区警固1-1-23 ℡Fax092-714-0112 |
| 日 時 | 5月23日(日)10:30~12:00 |
| 定 員 | 20名 |
| 参加費 | 2500円(教材プリントあり) |
| 申し込み | 当局事務局へFAXまたメールでお願いします。 |